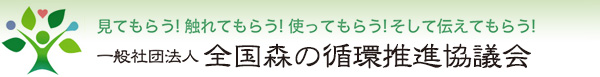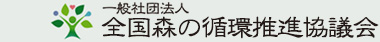| 2013/11/28 | 森の循環推進フォーラム2013 |
|---|

今回のイベントでは、第1部として、先日上棟を迎えました環境型住宅のフォレストアクアⅡについての上棟発表会。 第2部として、各県行政より来賓をお招きしまして、森林の保護・活用、国産材の活用に関しての意見交換の場として森の循環推進フォーラム2013が開催されました。

【第1部】 フォレストアクアⅡ 上棟発表会
1. 開会のご挨拶

◆森の循環推進協議会サポーター会 狩浦副会長より
2. 主催者代表ご挨拶

◆森の循環推進協議会サポーター会 越井理事より
『原木の価格高騰となっております昨今、受け口、出口を準備していくのが、我々の使命であります。菅沼社長の熱い思い、宅建協会のご支援のおかげで、ようやくここまで参りました。継続した活動を推進して参りますので、今後ともよろしくお願い致します。』
3.発表
先日11月12日に上棟となりました、フォレストアクアⅡについて、弊社建築担当、各協力業者より発表を行いました。
■フォレストアクアⅡ 建築過程の発表

◆㈱インテリジェンス・ネットワーク 建築担当より
■構造・羽柄材

◆栃木県集成材協業組合 落合部長より
「MSR試験について」
※機械等級の試験、木材を扱う場合、産地や木1本1本の強度の違いを、
1枚1枚測ったものを、色分けをしてあります。基準はJASに基づいております。

◆㈱タツミ 北関東工場 星工場長、豊後様より
・本社新潟での金物製造~制度 模型を使っての説明。

↑実際に使われている金物構造の模型。木材のみで組み合わせたものより、各段に強度が増します。
~上棟模様の写真とともに、事務局より 水源林見学の感想~
・間伐をしていない森林・している森林の比較
・水源林の学習、実験
『 森林維持の大切さ、間伐の大切さ、難しさを実感しました。
①川上にて森林維持・保全 ②森林間伐作業 ③山から木材を搬出
④搬出木材の加工 ⑤川下にて利用
このサイクルを回していくことが大切だと感じました。 』
*木材利用立米数、建築費用の木材利用費用比率、坪単価を発表
■木製サッシ

◆越井木材工業 宮下様より
↑手前にある模型が木製サッシのサンプルです。
「サーモウッド処理」が施されています。
・健全な森林の育成に必要な手入れ=1サイクル約60年
・構造材として安価な輸入材が入っており、育林にかける手間に見合ったお金が入らない。
・『地産外消』を推進していく
外装材など新しい使い方を開発 → 山間部の伐採、製材、搬出、植林・育林それらの雇用が生まれる→山の整備が進むので、森林資源の維持がなされ、都市部の木質化が進む。
・ウッドエンジニアリングの活用…木材に新しい性質を加える技術
・サーモウッド処理で弱点の克服(腐り・曲りなど)
・三ツ沢1期目および2期目での施工事例
・施工事例写真
■耐震ドア
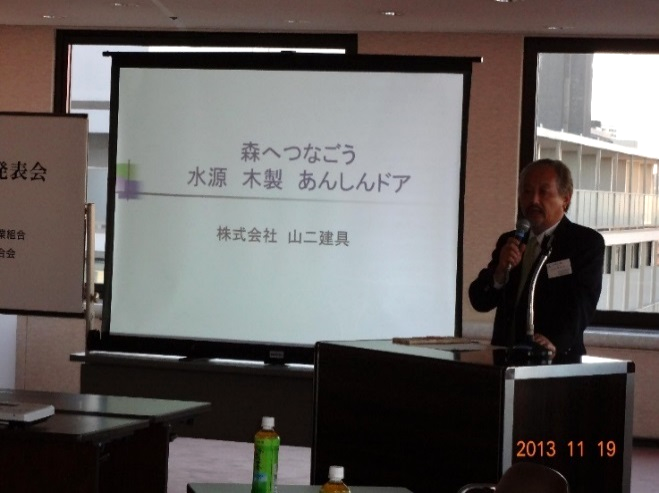
◆㈱山二建具 薮崎様より
“水源・木製あんしんドア” の発表
・「あんしんドア」とは?
災害時に起こる建物の歪みに機能を発揮
閉じ込め防止!避難経路確保!備えてあんしん!!
機能その1 『木口のR加工』
機能その2 『建築基準 対応』
機能その3 『試験結果』
・デザインの自由設計
木製建具製造工場によるハンドメイドの強み
設計段階よりお打合せが可能。
地域材のブランド化に対応可能。
木材利用ポイント。即時交換に対応。
・あんしんドアのサンプルでの実験体験

↑向かって右側が「あんしんドア」。枠組みに板を挟んで歪みを加えると、
通常のドアは開かなくなってしまいますが「あんしんドア」は簡単に開けることが出来ます。

↑「あんしんドア」の模型。木口にR加工を施すことで、枠が歪んでもドアが開閉できます。


↑左:フォレストアクアⅡの模型 右:横浜市にある戸建の環境型住宅の模型
フォレストアクアⅡは、各協力業者様の最新技術を結集して作られています!
続きまして、第2部の森の循環推進フォーラムについてご紹介いたします。
【第1部】 森の循環推進フォーラム 2013

進行 森の循環推進協議会サポーター会・副会長 狩浦様
参加 神奈川県 環境農政局
山梨県 森林環境部
横浜市 水道局
横浜市 建築局
◆神奈川県 環境農政局

「かながわの水源環境の保全・再生」
・“かながわ水源環境保全・再生実行5か年計画”(平成24年度~28年度)
『木材資源の循環による持続可能な人工林を目指しております。』
平成19~23年度 1期目 ⇒ 私有林からの搬出量増加、間伐の促進
平成24年~ ⇒ 新たな取り組みとして、鹿の採食による整備効果減少への対策
・かながわ水源環境保全・再生施策大網
期間 平成19年度~38年度
目的:良質な水の安定的確保
『間伐材利用の啓発活動を継続的に行って参りたいと思います。
御協力お願い致します。』
◆山梨県 森林環境部

・山梨県のPR、『明治45年の水害の経験より、恩師林としております。』
県有林 全国2位
県土面積率 35%で第一位
県の面積全体の内、森林面積の46%が県有林
→反面、急に需要が出てきたときに対応が困難。
・FSC認証森林 (森林管理協議会)
承認面積全国第1位
スギ・ヒノキ・カラマツ・あかまつの構成比がほぼ同比率である。
・木を育てる方向へ注力していたが、今後は活用へも注力してゆく。
105,000立方への拡大、木質バイオマスへ10万立方
隣県静岡の製紙工場も影響あり需要が見込める。
・今後の課題
木材市場の供給量不足
供給体制の整理
産学官の新たな取り組み。
上流~下流の連携 今後の啓発を持続して参りたい。
林業の充実化、道網の整理、県・森林組合で取り組んでいく。
木材市場について 急所の山、林業の拡大を図っていきたい。
南部地域、東部地域=相模原との連携を図る。
『素材生産量のひとつの目標は、ただ丸太を生産するだけでなく、県内で加工を行い首都圏で消費することです。県内へお金が入る仕組みを作っていくことが重要。』
ここで、質疑応答の一部を紹介いたします。
Q.越井顧問
「木材利用の関連性についてお聞きしたい」
A.神奈川県環境農政局
「木材・木造化、木材生産のために搬出しているのではなく、
内装の木造化、森林の間伐を進めるために、民間の方々に整備していただく。
木造化と間伐、両方進んでほしいのが正直である。」
Q.菅沼顧問
「 少し主旨が異なるかもしれませんが、
12,24ミリの県産合板についてお話をさせて下さい。
三ツ沢共同住宅(フォレストアクア)にて、初めて使用させていただきましたが、
現場に桧の香りがいっぱい漂っていて、御施主様も非常に喜んでおられました。
経済面ではなく、必要生産として活用を進めていければ。
また、一般の市民・県民による活用を進めていければと考えております。
お願いでもありますが、山梨県森林環境部の方からもお話がありましたが、
まずは、販路拡大。こちらを、山梨・神奈川で合同での拡大事業というのは、
可能でしょうか。
連携を取った上で、ユーザー様にご使用いただくということは可能でしょうか。」
A.神奈川県環境農政局
「決して連携をしないというわけではなく、前向きに検討したいと考えております。」
A.山梨県森林環境部
「富士山の世界遺産登録や、箱根などのブランド登録などのお話のように、
三つの県それぞれの事情があり、難しい部分もあります。
ですが、そういった連携の動きはあります。
神奈川県の話ですと、相模川の流域、山梨県桂川、県を超えて、流域材の供給体制
を民間主導で進めていくという構想もあります。
山梨・東部地域で、今後 神奈川・相模川地域の皆様と交流・話をする予定です。」
◆横浜市 水道局 「横浜水源の道志村 水源涵養林・間伐材利用について」

明治20年、相模川と道志川が合流する箇所から蒸気機関を使用していた。
燃料は石炭、燃料の不足問題 ⇒それらを解決するため、
支流である道志川からの取水を開始。
大正五年6月~ 山梨県から道志村所在恩県有林2780haを買収、
第10期(H18~H27年まで)管理計画を実施開始。
涵養林の面積は、2873haで横浜市の都筑区と同じ面積である。
・道志水源林(人工林・天然林)のはたらきについて
水源涵養林の管理⇒森林の保水機能を高め(はっ水緩和機能)、
安定した飲料水を供給するため
◆横浜市 建築局 「公共建築物について」
・11月20日まで検討
横浜市内では林業を推進しようとする部署がない。
その受け皿となる経済進歩の観点から、
横浜市環境政策局で行うか、建築局で行うか、庁内で検討した結果、
建築局で方針案を今年度中に作成することが目標。
・背景
木材利用に関する法律の制定。
十分に行われていない、木を使うことによって林業を支えていこうという方針
公共建築物において、木材を使用する。
断熱性、調湿性、炭素50%以上、木材内に貯蔵している。
循環型社会の実現の可能な資源。
木の効果=防ダニ・癒しの効果・ストレスの緩和
公共建築物に木材を使用することは、地球温暖化を防止する低炭素社会の実現を
目的とする。
公共の低層の建物(公園内、コミュニティーハウス等)は原則木質化。
各県行政の方々より、現在の木材利用についての貴重なお話を伺うことが出来ました。
各県、各局それぞれの視点から木材利用を考えることで、利点や問題点が多く浮かび上がってきました。
その他、以下の方々へもお話を頂くことが出来ました。
◆河津顧問 「小国の林業について」…“地熱乾燥材”の紹介
◆神奈川森林組合 「県産合板の実情と今後の使用お願い」
◆ 星副会長「質問:(木材利用推進について)産地偽装を行った場合、
罰則などがあるのでしょうか?」
横浜市建築局「あくまで木材利用を推進するという『方針』なので、罰則はありません。
100%国産材使用出来るとは限らないので、そういった部分ついては今後検討しながら対応していく予定です。」
◆横浜国大 西川コーディネーター「産官学の連携について」
◆横浜国大 中尾博士「木材のもたらす効果、データ、利用する目的についての意見」
以上で、森の循環推進フォーラム2013は終了となりました。
神奈川県、山梨県、横浜市が一堂に会し、森林・木材利用に関しての意見交換を行えたことは、協議会の活動において大きな一歩となりました。
それぞれの立場からの意見を共有することで、視野を広げることが出来た反面、
課題も多く残っておりますが、一つ一つ、地道に活動を継続していくことが重要だと感じました。
まずは、関心を持って頂くこと。HPをご覧の皆様にも、私たちの生活と、森林・水源地が密接に繋がっているということを少しでも感じていただけたら幸いです。
次回の協議会イベントは、来年3月のフォレストアクアⅡ完成予定に合わせて行う予定です。
都道府県のエリアを越え、流域の川上・川下の産官学が一体となることを目指し、今後も活動をしていきます!!
最後までご覧頂きまして、ありがとうございました。

↑産業貿易センター9F 横浜シンポジアからの眺め。
森の循環推進協議会 事務局より